「身長が低いから消防士は無理かも…」その不安、私が解消します!
この記事では、身長が低くても消防士になれるのか、そして現場でどう活躍できるのかを、現役の166cmの「チビ消防士」である私が徹底解説します。
結論から言うと、身長が低くても消防士になれます!
かつて約20年前までは身長・体重の制限を設ける自治体もありましたが、現在は東京消防庁をはじめ、ほとんどの市町村でそのような身体的な条件は撤廃されています。(ごく一部例外がある場合もあるので、志望先の募集要項は確認してくださいね。)
私自身のリアルな体験に基づき、低身長だからこそ活きるメリットと、知っておきたいデメリットを包み隠さずお伝えします。ぜひ、あなたの夢への一歩の参考にしてください!
低身長消防士のメリット:体型が「適材適所」になる時代
1. 狭隘(きょうあい)空間での機動力が高い
低身長は、大型の隊員には不可能な狭い場所での活動を可能にします。
- 【救急】 狭いアパートの部屋、自宅の廊下、そして救急車内での活動は、体が小さい方が圧倒的に動きやすいです。限られたスペースでの機敏な動きは、活動のスピードに直結します。
- 【火災】 消火活動に必要な空気ボンベ(呼吸器)は、消防車内で装着します。身長が高い隊員は車内で体が突っかかったり、身動きが取れなくなったりすることが多々ありますが、低身長であればスムーズに装着し、素早く現場に向かえます。
- 【救助】 地震などで建物が崩れた際、要救助者(助けられる人)がいる隙間や瓦礫の下など、大型の隊員が入れない場所に進入し、救助活動を行えるのは低身長隊員ならではの大きな強みです。
2. 俊敏性・機動性を活かせる競技や訓練がある
消防の訓練や、技術を競う大会では、低身長・軽量であることが有利になる競技がたくさんあります。
例えば、ロープを使った訓練や、素早い身のこなしが求められる競技では、低身長の隊員が全国大会で活躍している例は少なくありません。
もちろんパワーが求められる場面もありますが、「俊敏性」「バランス感覚」「器用さ」が重要になるポジションでは、低身長が大きなアドバンテージとなります。
低身長消防士のデメリットと克服方法
正直にお伝えしますが、現場では低身長ゆえのデメリットも存在します。しかし、これらは努力で必ず克服できるものです。
1. 重量物の「運搬」や「搬送」で不利になる場合がある
身長が低いと体重も軽い傾向があるため、重い資機材や、救急現場での傷病者(病気や怪我をした人)の搬送作業において、体格の大きな隊員に比べて不利になることがあります。
(体が大きい方が、筋肉が長く、より大きな力を発揮しやすいためです。)
✅ 克服策: 体格差は技術で埋めましょう。効率的な持ち上げ方・運び方の技術を磨き、筋力トレーニングを徹底して行えば、このデメリットは十分に克服できます。
2. 放水時の「反動」に体力を奪われやすい
火災現場での放水は長時間にわたることが多く、水圧によるホースの強い反動を抑え込むために大きな体力を使います。
身長が低く体重が軽い場合、この反動を抑えることに体力を奪われやすく、不利になることがあります。
✅ 克服策: これは体幹(コア)の強さが非常に重要になります。体幹トレーニングや下半身の筋力強化を徹底することで、反動に負けない安定した放水姿勢を作ることができます。
結論:低身長は弱点ではなく「最強の個性」である
この記事を読んでお気づきの通り、低身長消防士が抱えるデメリットは、筋力トレーニングや技術の習得によってすべてカバー可能です。
しかし、狭隘空間での機動力など、低身長だからこそ得られるメリットは、他の誰にも手に入れることができない「あなただけの強み」です。
現代の消防は、多様な災害に対応するため、様々な体格の隊員が活躍できる「適材適所」の組織へと進化しています。
身長が低いからと消防士の夢を諦めかけている方へ。
自信を持って、消防士を目指してください。
「あなたにしか入れない場所」、「あなたにしかできない活動」は必ずあります。その日のために、今から準備を始めましょう!

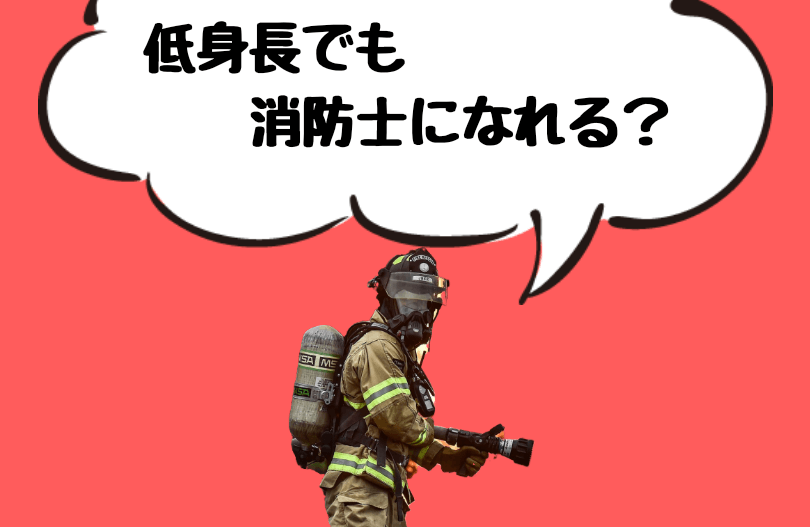
コメント