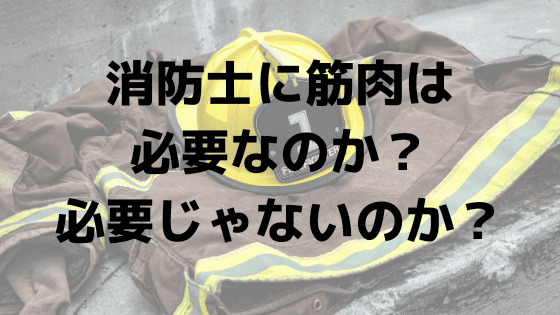【現役が断言】消防士に筋肉は必要ない!体力不安を抱える帰宅部出身者が語る真実
「消防士になりたいけど、運動経験がないから無理だ…」
「筋肉には自信があり、それを生かした仕事をしたい。」
現役消防士、救急救命士の凜(@mappletour)です。
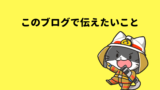
消防士と聞くと、多くの人が「鍛え抜かれた肉体」や「激しいトレーニング」をイメージするでしょう。
かくいう私も、高校3年間帰宅部で、体育の授業では大の苦手なお荷物でした。当然「消防士は無理だ」と体力不安でいっぱいだったのを覚えています。
でも、結果的に私は厳しい消防学校を乗り越え、現役の消防士として10年以上働けています。
消防士に筋肉は必要なのか?結論から言えば、体力に不安がある人でも諦める必要はありません。元帰宅部の私が、あなたの不安を解消するその理由を包み隠さずお伝えしましょう。
1. 【現役が語る】それでも「筋肉が必要」と言われる3つの理由

「筋肉は必要ない」と断言する前に、まずは消防士の仕事のリアルとして、なぜ体力が求められるのかを理解しておきましょう。
装備の重量が重いので筋肉は必要!
火災現場へ向かうとき、消防士は防火衣や空気呼吸器(ボンベ)を背負います。
その重量は、動きにくい厚手の防火衣で約10kg、空気呼吸器が約8kgと、合計で約18kgにもなります。この重い装備を普段の作業服の上から着込み、さらに資機材を持って現場で活動し続けなければならないため、基礎体力や筋肉が必要不可欠です。
放水には反動に耐える力が必要!
火を消す際の放水作業は、想像以上に体力を消耗します。
ホースは1本(20メートル)で約10kg。それに加えて、ノズルから水を出すときには、水そのものの重さに強烈な反動が加わります。体力や筋肉に自信がある消防士でも、体勢をしっかり整えないと吹っ飛ばされるくらいの力が発生します。
現場活動は長時間に及ぶので筋肉は必要!
火災現場での活動がすぐに終わることは稀です。私たちは最低でも3時間は覚悟して活動に臨みます。
約18kgの重装備を身につけ、重いホースと反動に耐えつつ、火の熱さや煙たさといった極度のストレスの中で活動し続けるには、当然ながらタフな体力と筋肉が求められるのです。
2. 消防士に筋肉が必要ないと言える3つの理由【体力不安を解消】

体力が必要な場面があるのは事実です。ではなぜ、帰宅部で懸垂が6回しかできなかった私が消防士になれたのでしょうか? その秘密は、「道具の進化」と「仕事の質」にあります。
(理由1)進化した道具!ホースの軽量化と水損防止
近年、現場で重要視されているのが「水損防止」という考え方です。これは、必要最低限の水で消火し、消火後の水による被害を防ぐための対策です。
少水量で効率的に消火する現代の消防技術が発展した結果、ホースも細く軽量化されました。これにより、ホースの取り回しが楽になり、体力勝負から、少水量を効率的に扱う技術勝負へとシフトしているのです。
(理由2)少ない力で放水可能に!ノズルの進化(ガンタイプ)
放水ノズルの形状も進化しています。
以前のただの筒状のノズルから、現在では人間工学に基づいて握りやすい「ガンタイプ」が主流です。持ちやすくなったことで反動に耐えやすくなり、以前よりも少ない力で安定した放水が可能になりました。これは、筋力に自信のない人にとっては大きな助けとなります。
(理由3)体力試験は「動ける身体か」のチェック。筋肉量が合否を決めない
消防士の採用試験には体力試験がありますが、これは「消防士として訓練に耐え、働ける基礎的な身体能力があるか」を測るものです。
体力があればあるほど合格に近づくわけではありませんし、ベンチプレスで何キロ上がるかといった筋肉量が合否を決めることはありません。
実際、高校3年間帰宅部で懸垂6回だった私でも、基礎体力さえクリアすれば採用されました。合格後、必要な体力は厳しい訓練で十分に身につけられますから、体力不安で夢を諦めるのはやめましょう。
3. 【まとめ】消防士は「体力」より「頭の良さ」が問われる時代へ

結論として、体力に不安があるからといって消防士の夢を諦める必要は一切ありません。
たしかに筋肉や体力はあればあるほどいいですが、現場の道具が進化し、「省力化」が図られているのが現代の消防活動の現実です。
今、消防士に求められているのは、その道具を使いこなし、現場で最適な判断を下す「頭の良さ」です。
体力不安で夢を諦めるのはもったいない!まずは知識をつけ、採用試験に備えることが合格への近道です。
【行動への一歩】
まずは体力試験の最低基準をクリアするために、基礎的なランニングや筋トレから始めてみましょう!